Ethereum 相互運用性ロードマップ: 大規模導入への「ラストマイル」を解き放つ方法
- 核心观点:互操作是跨链叙事的终极形态。
- 关键要素:
- 以太坊基金会将互操作定为核心战略。
- 聚焦初始化、加速、最终确定三阶段。
- 缩短提款时间提升流动性效率。
- 市场影响:推动多链无缝协作,提升用户体验。
- 时效性标注:中期影响。
Web3 の世界では、「クロスチェーン」から相互運用性まで、常に話題になっています。
もちろん、両者の意味合いを厳密に区別していない人も多いでしょう。一言でまとめると、クロスチェーンは資産に重点を置き、主に「移転」の問題を解決します。一方、相互運用性は資産、状態、サービスといった複数の側面をカバーし、「連携」の問題を解決することを目指します。
実際、モジュール型のナラティブによってL1/L2の数と異質性が増すにつれて、ユーザーと流動性はさらに分散化しています。相互運用性は、クロスチェーンよりも理想的な最終目標として認識されています。ユーザーはもはやどのチェーンに属しているかを意識する必要はなく、一度インテントを送信するだけで、システムは最適な実行環境で自動的に操作を完了します。
Ethereum Foundation (EF) による最近の新しい UX ロードマップの発表と、引き出しの遅延、メッセージング、リアルタイム証明を取り巻く一連のエンジニアリングの進歩により、相互運用性のパズルが体系的に組み立てられつつあります。
1. 「Interop」とは何ですか?
簡単に言えば、「相互運用性」は単なる「資産の橋渡し」ではなく、システムレベルの機能全体を組み合わせたものなのです。
これは、異なるチェーンが状態と証明を共有でき、スマート コントラクトが互いのロジックを呼び出すことができ、ユーザーは統一されたインタラクティブなエクスペリエンスを得ることができ、すべての実行環境がセキュリティ境界で同等の信頼性を維持することを意味します。
これらの機能が同時に実現されると、ユーザーはネットワークの切り替え、重複した承認、流動性の断片化に煩わされることなく、真に価値活動そのものに集中できるようになります。これは、クロスチェーンエンジニアリングの究極の目標、つまりユーザーがチェーン間の障壁ではなく、価値の流れそのものに集中できるようにすることにも合致しています(参考文献:「クロスチェーンエンジニアリングの進化:『アグリゲーションブリッジ』から『アトミック相互運用性』へ、私たちはどのような未来に向かっているのか? 」)。
特に 2024 年に入ってからは、モジュール化の話が本格的な爆発期に入り、ますます断片化された L1 層と L2 層が登場し、相互運用性はもはやプロトコル層での高レベルの話ではなく、一般ユーザーのユーザー エクスペリエンスと基礎となるアプリケーション ロジックに真に浸透し始めました。
意図中心の実行アーキテクチャであれ、クロスチェーン集約やフルチェーン DEX などの新しいアプリケーションであれ、それらはすべて同じ目標を追求しています。つまり、ユーザーと流動性が Ethereum メインネットに限定されず、ネットワークを頻繁に切り替えることもなく、オンチェーン資産交換、流動性提供、戦略操作を統一されたインターフェースでワンストップで完了できるようにすることです。
言い換えれば、相互運用性の究極の可能性は、ブロックチェーンをユーザーの視点から完全に排除することにあります。つまり、DApps とプロジェクトチームがユーザー中心の製品パラダイムに戻り、使いやすく Web2 に近いエクスペリエンスを提供する障壁の低い環境を作成し、ブロックチェーン外部のユーザーが Web3 の世界にシームレスに参入するための最後の障害を取り除くことにあります。
結局のところ、製品の観点から言えば、主流への導入の鍵は、誰もがブロックチェーンを理解できるようにするのではなく、理解することなく利用できるようにすることです。Web3を数十億人の人々に届けるためには、相互運用性こそが「ラストマイル」を支えるインフラと言えるでしょう。
8月29日、イーサリアム財団は「プロトコルアップデート 003 - UXの向上」をリリースしました。この記事では、今年のR&Dチーム再編後のEFの3つの主要な戦略方針である、Scale L1(メインネットのスケーリング)、Scale Blobs(データのスケーリング)、Improve UX(ユーザーエクスペリエンスの向上)について引き続き解説しています。
そして、「UX の向上」の中心的なテーマは相互運用性です。
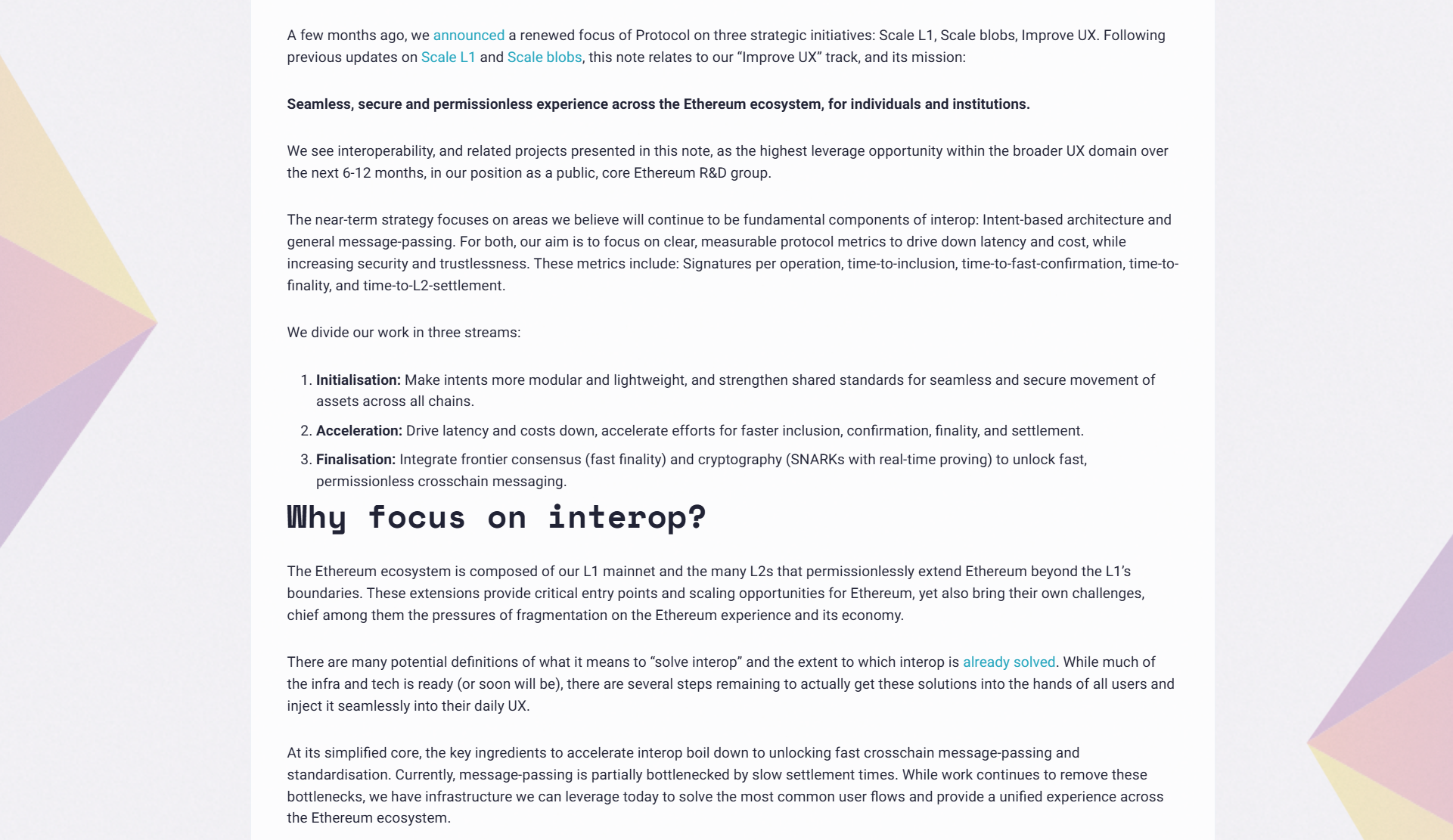
出典: イーサリアム財団
II. 「クロスチェーン」から「相互運用性」へ:EFが発信するシグナル
このEFの記事は、シームレスで安全、かつパーミッションレスなEthereumエコシステム体験の実現を目指し、相互運用性を中核に据えています。要点は一言でまとめられます。クロスチェーン資産移転は単なる第一歩に過ぎず、データ、ステート、サービスのクロスチェーン連携こそが真の「相互運用性」です。将来的には、EthereumはすべてのRollupとL2を「一つのチェーンのように見せる」ことを計画しています。
もちろん、EF は、インフラストラクチャとテクノロジーの大部分は成熟している(または成熟しようとしている)ものの、これらのソリューションをユーザーに実際に提供し、ウォレットと DApps の日常的なエクスペリエンスに自然に統合するには、いくつかの重要なエンジニアリング実装手順がまだ必要であると認めています。
そのため、EF では、「UX / 相互運用性の向上」の開発を、初期化、加速、および終了という 3 つの並行するメイン ラインに分割します。
最初のステップは「初期化」であり、相互運用性の出発点となり、イーサリアムのクロスチェーン動作をより軽量かつ標準化することを目指しています。
中核となる作業には、インテントをより軽量かつモジュール化すること、共通標準を確立すること、クロスチェーン資産とクロスチェーン操作の間の橋渡しをすること、さまざまな実行レイヤーに交換可能かつ構成可能な共通インターフェースを提供することなどが含まれます。
実施された具体的なプロジェクトは次のとおりです。
- Open Intents Framework (OIF): EF、Across、Arbitrum、Hyperlane、LI.FI、OpenZeppelin などが共同で構築したモジュール式のインテント スタック。さまざまな信頼モデルとセキュリティの前提を自由に組み合わせることができます。
- Ethereum 相互運用性レイヤー (EIL): ERC-4337 チームが主導し、許可がなく検閲に強いクロス L2 トランザクション トランスポート レイヤーを構築し、マルチチェーン トランザクションを単一チェーンと同じくらい自然にします。
- 新しい一連の標準 (ERC シリーズ): 相互運用可能なアドレス (ERC-7828/7930)、資産統合 (ERC-7811)、複数の呼び出し (ERC-5792)、意図および一般的なメッセージング インターフェイス (ERC-7683/7786) をカバーします。
目標は単純です。 「ユーザーが何をしたいのか」(宣言的)と「システムがそれをどのように実行するのか」(手続き的)を切り離し、ウォレット、ブリッジ、検証バックエンドが統一されたセマンティック フレームワークの下で連携できるようにすることです。
2 番目のステップは「アクセラレーション」です。これにより、レイテンシとコストが削減され、マルチチェーン操作がよりリアルタイムになります。
具体的には、時間とコストの削減は、「署名数、インクルード時間、高速確認、ファイナリティ、L2決済」といった測定可能な指標を中心に展開されます。主要な施策としては、L1高速確認ルール(強力な確認を15~30秒に短縮)、L1スロット時間の短縮(12秒から6秒への短縮に向けた研究開発)、L2決済/出金期間の短縮(楽観的な7日間を1~2日に短縮、またはZK証明と2/3高速決済メカニズムの導入)などが挙げられます。これらの施策は、本質的にクロスドメインメッセージパッシングと統一されたエクスペリエンスの基盤を築くものです。
最終的に、「最終決定」ステップでは、リアルタイムSNARK証明とより高速なL1ファイナリティを組み合わせ、第2レベルのファイナリティを備えた相互運用性モデルを模索します。長期的には、これはクロスドメイン発行、ブリッジングプリミティブ、そしてクロスチェーンプログラマビリティのあり方を大きく変えるでしょう。
客観的に言えば、Ethereum のコンテキストでは、Interop はもはや「アセット ブリッジ」の概念に限定されず、むしろシステム レベルの機能全体を表す総称になります。
- クロスチェーンデータ通信- 異なる L2 が状態や検証結果を共有できます。
- クロスチェーンロジック実行- 1 つのコントラクトが別の L2 のロジックを呼び出すことができます。
- クロスチェーンのユーザー エクスペリエンス- ユーザーは複数のチェーンではなく、1 つのウォレットと 1 つのトランザクションのみを表示します。
- クロスチェーンセキュリティとコンセンサス- 証明ベースのシステムを通じて、異なる L2 ブロックチェーン間で同じセキュリティ境界を維持します。
この観点から、Interopは将来のEthereumエコシステムプロトコルにおける共通言語として理解できます。その意義は、価値の伝達だけでなく、ロジックの共有にも存在します。
III. イーサリアムはどのようにして「相互運用性」への道を切り開くのでしょうか?
注目すべきは、Vitalik 氏が最近、Ethereum Magicians フォーラムで、ステージ 1 の楽観的集約引き出し時間の短縮について議論を開始し、引き出しサイクルを従来の 7 日から 1 ~ 2 日に短縮することを提唱し、制御可能なセキュリティを前提として、より高速な決済および確認メカニズムを段階的に導入することを提案したことです。
この議論は、一見すると Rollup の撤退体験に関連していますが、実際には「相互運用性」の 3 つの主要な方向性の 1 つである加速に対する直接的な反応です。
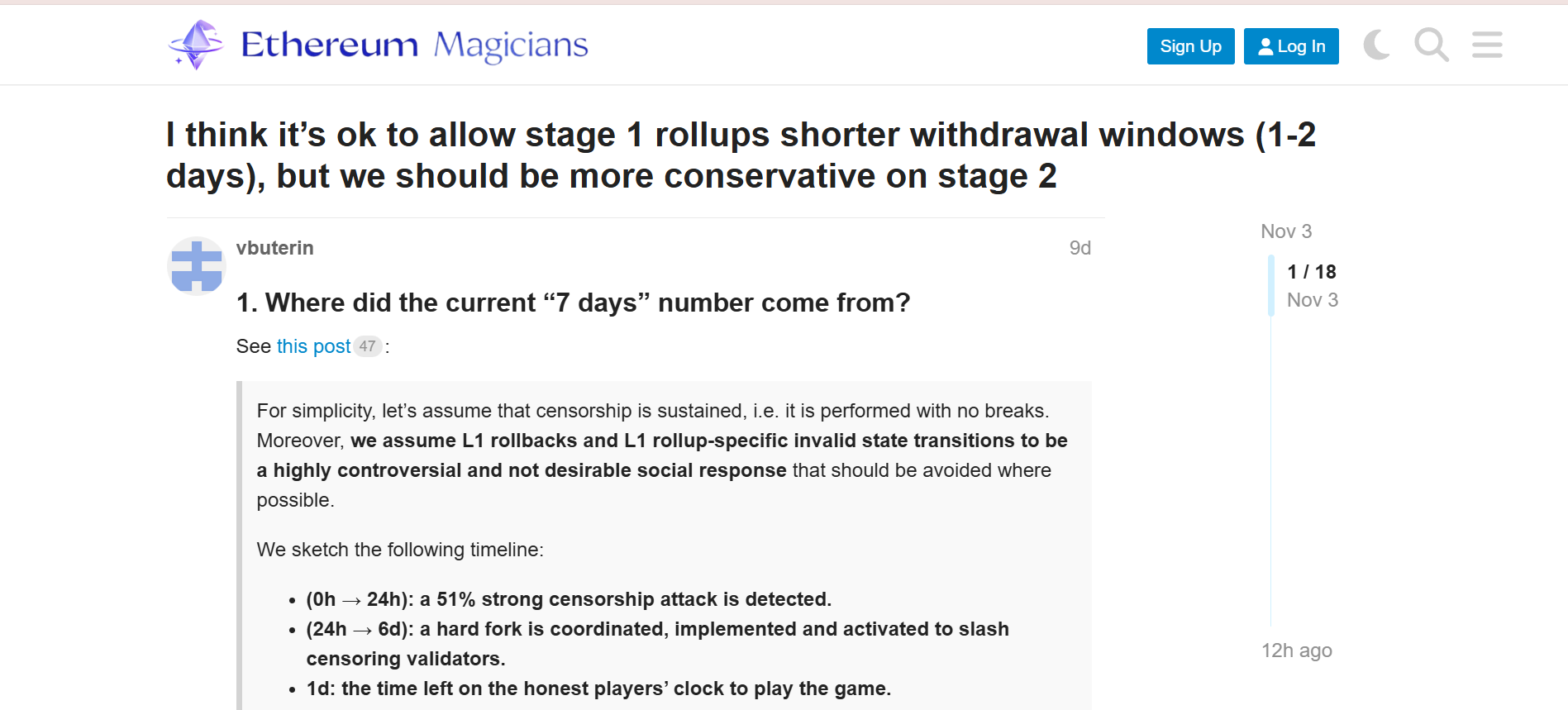
出典: イーサリアムマジシャンズ
結局のところ、出金の遅延は、単に待ち時間が長すぎるというユーザーエクスペリエンスの問題ではなく、マルチチェーンコラボレーションシステム全体の流動性のボトルネックです。
- ユーザーにとっては、異なるロールアップ間で資金がどれだけ速く流れるかを決定します。
- インテント プロトコルとブリッジ ネットワークの場合、ソリューションの資本効率に影響します。
- Ethereum メインネットの場合、高頻度のインタラクションの中でエコシステムが一貫性とセキュリティを維持できるかどうかを決定します。
Vitalik氏の見解は、本質的にこの流れを加速させるものです。つまり、出金時間の短縮は、Rollupsのユーザーエクスペリエンスを向上させるだけでなく、クロスドメインメッセージング、流動性、そして迅速な状態遷移のためのインフラアップグレードを可能にします。この方向性は、EFの「アクセラレーション」メインラインにおける目標とも完全に一致しています。つまり、確認時間の短縮、決済速度の向上、輸送中の資金調達コストの削減、そして最終的にはクロスチェーン通信のリアルタイム性、信頼性、そして構成可能性を実現することです。
これらの取り組みは、11月17日にアルゼンチンで開催されるDevconnectイベントに合わせて行われます。公式アジェンダによると、今年のDevconnectでは相互運用性が主要テーマの一つとなり、EFチームは同イベントでEIL(Ethereum Interoperability Layer)に関する詳細も発表する予定です。
全体的に、すべては同じ方向を指しています。つまり、イーサリアムは「スケーリング」から「統合」への変革を完了しつつあります。
もちろん、この記事は、Interop シリーズの最初の記事として、相互運用性がクロスチェーン ナラティブの究極の目標であるという根本的な疑問を提起するだけであり、EF の技術ロードマップから Vitalik のリアルタイムの議論、標準化されたエンジニアリング レイアウトから徐々に短縮される決済サイクルまで、Ethereum エコシステムの現在の構造的アップグレードを垣間見ることができます。
相互運用性が単なる架け橋ではなく、イーサリアムの将来を結びつける基盤となるプロトコルでもある理由を、さまざまな観点から引き続き探求していきます。
乞うご期待。



