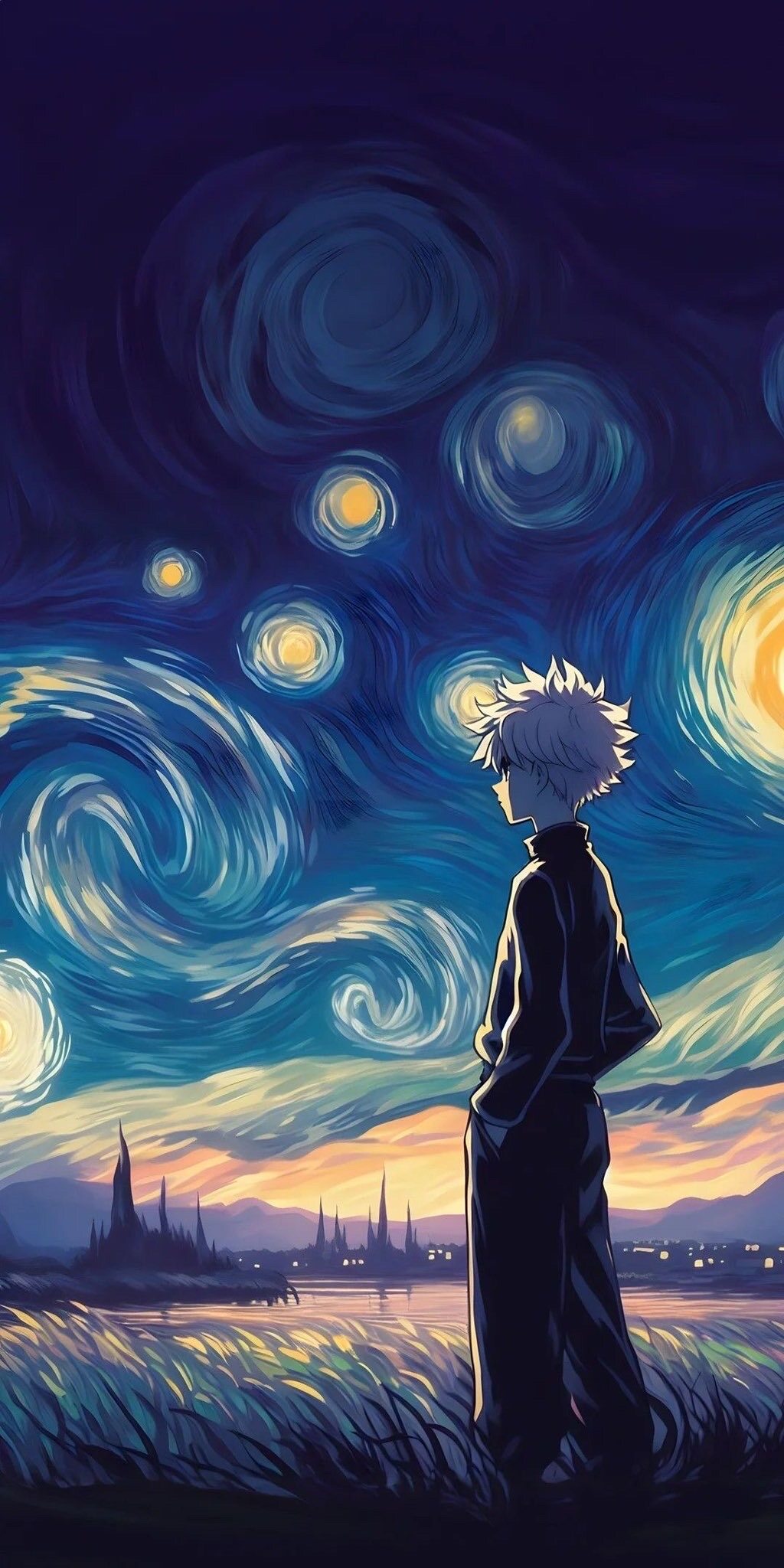仮想通貨の税率を20%に改革する日本の計画は新たな買いの流れをもたらすか?
- 核心观点:日本拟将加密货币税率从55%降至20%。
- 关键要素:
- 加密资产或由支付法转金融法管辖。
- 改革已获内阁决定,需跨党协商。
- 目标年底前敲定,2026年落实。
- 市场影响:或刺激日本加密市场活跃度提升。
- 时效性标注:中期影响。
オリジナル | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
ウェンザー( @wenser 2010 )
先日終了したWebXイベントにおいて、参議院議員で自由民主党(LDP)予算委員長の片山さつき氏(本名:片山さつき)は、日本が現在、暗号資産自体の再分類、特にBTCやETHといったよく知られた暗号投資資産の再定義を検討している と述べた。日本の暗号資産に対する現在の税率は55%と高いが、暗号資産が資金決済法から金融商品取引法に移行すれば、税率は株式税率と同程度の20%に引き下げられる可能性がある。彼女はまた、「この改革は1~2年以内に実施される予定で、早期に施行されることを期待しています。この改革の方向性は内閣で決定されており、通常は力強く推進されます。しかし、自民党が議席の過半数を失ったため、他政党との交渉が必要になります。これには時間がかかり、プロセスも複雑になりますが、複数の政党が私たちの考えに賛同しており、事態の進展を見守るつもりです。12月までに最終結論を得る必要があります」と述べました。
Odaily Planet Dailyはこの記事でこの点を詳細に分析し、この税率改革が暗号通貨市場にさらなる変動をもたらす可能性があるかどうかを探ります。
暗号通貨の税率は変更が必要:「新資本主義」下の経済的ジレンマ
日本の金融庁が開始し、自民党が主導する仮想通貨税制改革を詳しく見てみると、その主な動機が現在の日本のやや劣悪な経済環境にあることがわかる。
厚生労働省が7月上旬に発表したデータによると、物価調整済みの実質賃金は5月に前年同月比2.9%減となり、4月の改定値2.0%減からさらに下落し、2023年9月以来の大幅な下落となった。さらに、厚生労働省が実質賃金(生鮮食品価格をカバーし、家賃は除く)の算出に用いる消費者物価指数(CPI)は5月に前年同月比4.0%上昇し、名目賃金の上昇率を大幅に上回った。日本の米価は5月に前年同月比101.7%高騰し、半世紀以上ぶりの大幅な上昇となった。
物価高騰に加え、過去の内閣の失言や商品券不正問題も重なり、与党である自民党の信頼性は揺るがされている。7月21日、第27回参議院選挙の開票が終了した。 自民党と公明党による連立与党は、参議院の過半数維持に必要な50議席に届かず、合わせて47議席にとどまった。さらに、衆議院で過半数を確保できなかったため、連立与党は両院で少数与党政権となった。1955年の自民党結党以来、自民党主導の連立与党が両院で過半数を失ったのは初めてである。
さらに、日米関税交渉は日本経済の足かせとなり、内外の経済情勢の変動や展開にも影響を与えています。日本は今、内外両面で困難な状況に直面しています。そのため、日本政府は「新しい資本主義」というアプローチのもと、新たな解決策を模索せざるを得ません。具体的には、以下の2つの取り組みを進めています。
一方、最低賃金の引き上げは国民にとって新たな収入源となる。厚生労働省の中央最低賃金審議会は8月初旬、2025年の全国加重平均最低賃金の目安を1時間あたり1,118円(約54.60人民元)に引き上げることを決定した。これは現行の1,055円から63円(6%)の引き上げとなる。これは2002年の時給制導入以来、最大の増加額となる。日本における最低賃金の引き上げは23年連続となる。実施されれば、すべての都道府県で時給が初めて1,000円を超えることになる。
もう一つのアプローチは、減税によって公共支出を削減することです。現在、この方法は党派対立によって制限されており、まだ初期段階にあります。自民党は長年、暗号資産の再分類と税率引き下げを推進し、Web 3産業発展の拠点としての日本の地位向上に尽力してきました。しかし、立憲民主党や民進党といった野党も選挙で同様の政策公約を掲げてきました(民進党の玉木雄一郎代表が提唱したNFTやWeb 3対策など)。その結果、少数与党政権発足後、自民党の税制改革は「富裕層減税」との批判を避けるため、必然的に遅れをとってきました。だからこそ、暗号資産税制改革は、暗号資産を資金決済法で規制される「決済手段」から金融商品取引法上の「金融商品」へと転換させるという、新たな突破口と捉えられているのです。
これにより、仮想通貨の譲渡益は、地方税を除く「雑所得」として最大55%(所得税45%+住民税10%)の累進課税から、株式や債券などと同じ一律20%の課税に軽減される。
日本の二段階税制改革戦略:まず税法を改正し、次に監督を強化する
日本の税制改革は一朝一夕で実現できるものではないことを指摘しておくべきでしょう。さらに、暗号資産は資金決済法(PSA)と金融商品取引法(FIEA)の相互改正を伴うため、サイクルが複雑化しています。また、金融庁(FSA)の見直しや国会政策の影響も受けます。
現在、日本の税制改革は2段階で実施されます。
その第一歩は、税法改正、つまり仮想通貨を「総合課税」から株式などと同じ「分離課税」に調整し、税率を20%程度(所得税15%+住民税5.015%+復興特別税)に引き下げることだ。
第二段階は、規制の強化、すなわち法改正を通じて仮想通貨を金融商品として再分類し、金融庁が金融商品取引法に基づくインサイダー取引規制、情報開示基準、投資家保護措置を適用できるようにすることである。
仮想通貨税制改革の裏側:仮想通貨ETFと日本円ステーブルコインが準備完了
注目すべきは、これらの改革は、日本の規制当局が仮想通貨ETFや円建てステーブルコインの導入への道を開くための一歩とも捉えられていることです。日本における仮想通貨の現在の発展の停滞は、マウントゴックスのビットコイン盗難事件などのセキュリティインシデントによるものであることは間違いありません。また、高い税率も、仮想通貨業界における取引活動をある程度制限してきました。
日本仮想通貨ビジネス協会副会長の白石氏の統計によると、世界の仮想通貨市場が8,720億ドルから2兆6,600億ドルに拡大する中、日本国内の取引量は2022年の666億ドルから今年は推定1,330億ドルにしか増えておらず、成長率はわずか2倍程度にとどまっている。
一方、コーネル・ビットコイン・クラブが実施した調査では、日本人居住者の88%がビットコインを所有したことがないことが明らかになった。しかし、野村ホールディングスとレーザーデジタルが共同で実施した調査では、日本の機関投資家の54%が3年以内に暗号資産に投資する予定であることがわかった。
上記の情報に基づくと、暗号資産税制改革、暗号資産ETFの立ち上げ、そして日本円建てステーブルコインの導入が差し迫っている。 報道によると、日本の金融庁が承認した初の日本円建てステーブルコインであるJPYCは、東京に拠点を置く同名のフィンテック企業が発行する。同社は3年以内に1兆円(約67億8000万ドル)相当のステーブルコインを発行する計画だ。このステーブルコインは預金や国債などの流動性の高い資産を裏付けとし、国際送金、法人決済、DeFiなどへの活用が期待されている。日本で2番目に大きな銀行である三菱UFJフィナンシャル・グループ(SMBC)も以前、Ava LabsおよびFireblocksと提携してステーブルコインを発行する計画を発表している。
仮想通貨などの新興産業は、日本の社会発展の「生命線」とみなされている。
日本政府が仮想通貨業界を重視しているのは、新興セクター、特に仮想通貨に代表されるセクターの成長ポテンシャルを認識しているからです。東京で開催されたWebX 2025カンファレンスにおいて、石破茂首相は、「地政学的不確実性が高まる中、経済成長の新たな道筋を探るには、新興産業の力が不可欠だ」 と述べました。日本政府は、投資支援や規制改革を通じて、Web 3を含むデジタル、半導体、AI、宇宙産業の発展を促進し、新興産業の環境整備に引き続き取り組んでいきます。
石破茂氏はまた、日本の人口減少の根本的な原因は東京への人口集中にあり、それが結婚率と出生率の低下を招き、悪循環を生み出していると指摘しました。この歴史的な局面において、政府はWeb 3のような新技術の可能性を活用し、日本社会の活性化を図りたいと考えています。Web 3技術は、政府が推進する様々な改革に貢献することができます。デジタル技術の革新的な応用を通じて、産業競争力の強化だけでなく、地域振興や人口動態の変化といった社会課題に対する新たな解決策を提供することも可能です。
結論:税率改革はいつ始まり、いつ実施されるのか?
日本の法制度に基づくと、税制改革は通常、毎年12月に大綱が公表され、翌年の3月または4月に国会に提出され、6月頃に可決され、翌年の4月に施行されます。今回の仮想通貨税制改革はやや緊急性が高いため、年末までに具体的な提案が提出され、2026年初頭には法制化される見込みです。
正式な施行は2026年6月、あるいは年後半になる可能性もある。この法案を推進する主要人物には、自民党Web3プロジェクトチーム(Web3PT)の平将明氏と加藤勝信氏、日本銀行協会会長でビットバンク代表取締役の広末敬之氏、そして前述の自民党参議院議員で予算委員長の片山さつき氏などが名を連ねている。
その時までに、市場は新たな買いの波を迎えると予想されている。